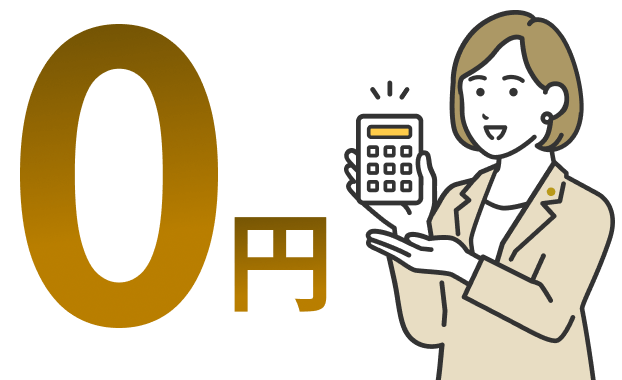デジタル資産の相続は? 流れや生前準備の注意点を弁護士が解説
- 遺産を残す方
- デジタル資産
- 相続

山口市の統計によると、令和5年の山口市の出生者数は1160名、死亡者数は2497名でした。
昨今の相続では、デジタル資産の扱いに戸惑う方もいるかもしれません。暗号資産(仮想通貨)やNFTなどのデジタル資産は、通常の資産と同様に相続の対象となります。
本記事では、デジタル資産の相続手続きについて、ベリーベスト法律事務所 山口オフィスの弁護士が解説します。


1、デジタル資産とは?
「デジタル資産(デジタル財産)」とは、デジタル形式の財産をいいます。たとえば、以下のものがデジタル資産に当たります
- 暗号資産(仮想通貨)
- 電子マネー
- クレジットカードのポイントやマイレージ
- 電子書籍や画像データなどのデジタル著作物、およびその著作権
- NFTアート
亡くなった人が保有しているデジタル資産は「デジタル遺産」または「デジタル遺品」と呼ばれることもあります。
2、デジタル資産の相続に関する問題点と対応策
デジタル資産も、預貯金や不動産などの財産と同様に、所有者が亡くなったら相続の対象になります。
デジタル資産の相続については、以下に挙げるような特有の注意点が存在します。弁護士などのサポートを受けながら、適切な形でデジタル資産の相続手続きを行いましょう。
-
(1)相続手続きが確立されているものと、そうでないものがある
デジタル資産は、日々新しい形態が登場するため、相続手続きの整備状況がまちまちです。
大企業が運営しているサービスにおいて保管されているデジタル資産については、比較的相続手続きが確立されているといえます。
たとえば、日本の暗号資産交換業者が保管している暗号資産(仮想通貨)や、電子マネーについては、保管先の企業に問い合わせれば必要となる相続手続きが分かるでしょう。
ただし、クレジットカードのポイントやマイレージについては、相続できないものとされているケースが多いので注意が必要です。できる限り生前の段階で使い切ることを検討しましょう。
また、デジタル著作物やNFTアートのように、保管用のサービスが確立されていない資産については、相続手続きが滞るおそれがあります。
相続手続きが複雑または不明確と思われるデジタル資産については、早い段階で売却して現金化する、弁護士に相談して必要な相続手続きを検討するなど、事前に対策を講じましょう。 -
(2)保管場所やアクセス方法が分からないことがある
デジタル資産は、目に見える形で存在しないため、遺族が発見しにくいという特徴があります。生前、直接聞いているか、または遺言書に記載されているのでなければ、そもそも存在するのかどうか、どこに保管されているのかが分からないでしょう。
また、デジタル資産の保管場所が分かったとしても、IDやパスワードが必要です。情報が共有されていない場合、取り出すことができず、事実上の喪失となるおそれもあります。
このような事態を防ぐには、生前の段階でデジタル資産をリスト化し、何らかの方法で相続人にアクセス方法を伝える必要があります。
たとえば、信頼できる親族や弁護士にリストとアクセス方法のメモを託し、本人が亡くなった際に相続人へ伝えてもらうなどの方法が考えられます。
また、デジタル資産をハードウエア(HDD、SSD、フラッシュメモリなど)において保管している場合は、定期的にバックアップをとっておきましょう。 -
(3)多額の税金が課されることがある
デジタル資産は、認知度が高まるに連れて価値が高騰するケースがあります。数年間で大幅に値上がりした暗号資産がその典型例です。
デジタル資産が取得時に比べて値上がりしている場合は、相続した際に多額の相続税が課され可能性があります。
また、相続したデジタル資産を売却した際には、値上がり益に対しても所得税と住民税が課されます。相続税と合わせると、思わぬ税負担が課されるおそれがあるので注意が必要です。
デジタル資産の相続に伴う課税で家族が苦しまないようにするためには、生前の段階で対策を行うことが大切です。多額のデジタル資産を保有している人は、弁護士や税理士に相談してアドバイスを受けましょう。
お問い合わせください。
3、デジタル資産の相続対策は弁護士に相談を
デジタル資産の相続に関しては、法律や税務などの観点からさまざまな注意点が存在します。弁護士のサポートを受けながら、生前からデジタル資産の相続対策を行いましょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- デジタル資産に特有の問題点を踏まえ、適切な相続対策について助言を得られる
- 相続税の申告や資産評価について、必要に応じて税理士等と連携して対応できる
- 相続人間のトラブルを避けるため、生前の準備や遺産分割協議の支援が得られる
- 煩雑なデジタル資産の相続手続きを任せられる
- トラブルが発生した際には、話し合いや裁判手続きの対応を任せられる
4、デジタル資産を相続する手続きの流れ
生前の段階から弁護士のサポートを受け、遺言書を作成するなどの相続対策を行っておけば、実際にデジタル資産を相続する際の手続きがスムーズに進みます。
弁護士と協力して行うデジタル資産の相続手続きの流れは、大まかに以下のとおりです。
-
(1)生前の相続準備
生前の段階では、以下のような対策を行うとよいでしょう。
生前にするデジタル資産の相続準備
- 所有しているデジタル資産の内容、保管場所、アクセス方法などをリスト化する
- 遺言書を作成する
- デジタル資産の相続手続きに必要な情報が、相続人に伝わるように手配する
- 相続できない、または相続手続きが煩雑なデジタル資産は使うか現金化する
弁護士のサポートを受ければ、デジタル資産の所有状況に応じた適切な相続対策を行うことができます。
遺言書についても、法律で定められた形式に従って有効なものをきちんと作成できるので安心です。弁護士を遺言執行者に指定すれば、本人が亡くなった際に、遺言書の内容を実現するための手続きを任せることができます。 -
(2)遺言書の有無と内容の確認
デジタル資産の所有者が亡くなると、相続が開始します。
相続人がまず確認すべきことは、遺言書の有無です。遺言書があれば、原則としてその内容のとおりに遺産を分割します。
遺言書が見当たらない場合は、遺品を確認したり、法務局や公証役場に保管されていないか照会したりする必要があります。
一方、生前に弁護士のサポートを受けて遺言書を作成していた場合する、弁護士が遺言書の存在を相続人に確実に伝えることが可能です。弁護士を遺言執行者に指定していれば、遺言書のとおりに相続手続きもスムーズになり、相続人の負担も減るでしょう。 -
(3)法定相続人と相続財産の調査
遺言書で財産の分け方が指定されていない場合は、相続人全員での話し合い、いわゆる「遺産分割協議」などによって分け方を決めます。
遺産分割協議を行うためには、まずは法定相続人と相続財産の調査が必要です。戸籍謄本などから、法定相続人と相続財産を確定しますが、個人の状況によっては戸籍が複雑になっていて調査に負担がかかることも少なくありません。
一方、遺言書によって相続財産を漏れなくリストアップしていれば、相続財産を調査する作業が必要ありません。念のための確認作業を行うとしても、相続人の負担を大幅に軽減することができます。 -
(4)遺産分割協議・調停・審判
財産を把握できたら、法定相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。相続人間で、それぞれの相続分に対して合意したら、その内容をもとに遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判を通じて遺産分割の方法を決めます。
遺産分割協議・調停・審判は、長期化するケースがよく見られますが、弁護士のサポートを受けながら遺言書を作成し、すべての相続財産について分け方を決めておけば、遺産分割協議などを行う必要がありません。
弁護士に遺産分割協議などの対応を一任すれば、よりスムーズな相続が期待できます。 -
(5)デジタル資産の名義変更
遺言書や遺産分割協議・調停・審判で決まった内容に従い、デジタル資産の名義変更を行います。
名義変更手続きは、デジタル資産の種類や保管場所などによって異なります。相続人が戸惑わないように、生前の段階で名義変更手続きの内容をまとめておくのが望ましいです。
名義変更手続きについては、弁護士に任せることもできます。また、遺言書作成の際に弁護士を遺言執行者に指定していれば、名義変更手続きを弁護士が代行するので、よりスムーズです。 -
(6)相続税の申告・納付
デジタル資産を含む多額の遺産を相続した場合は、相続税の申告が必要になることがあります。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議などが終わっていなくても、いったん期限内に相続税申告を行わなければなりません。
相続税申告は、税理士に依頼するのが安心です。ベリーベスト法律事務所グループには税理士も在籍しており、状況やご希望にあわせて弁護士と連携して対応することも可能です。
まずはお問い合わせください。
5、まとめ
デジタル資産は、ネットワーク上やハードウェアに保存されている無形の資産です。
預貯金や不動産などと同じく相続の対象となりますが、無形の資産に特有の注意点が多々存在するので、弁護士のアドバイスを受けながら相続対策を行うと安心です。
ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。所有しているデジタル資産について相続対策を行いたい方や、デジタル資産の相続手続きが分からずお困りの方は、まずはベリーベスト法律事務所 山口オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|