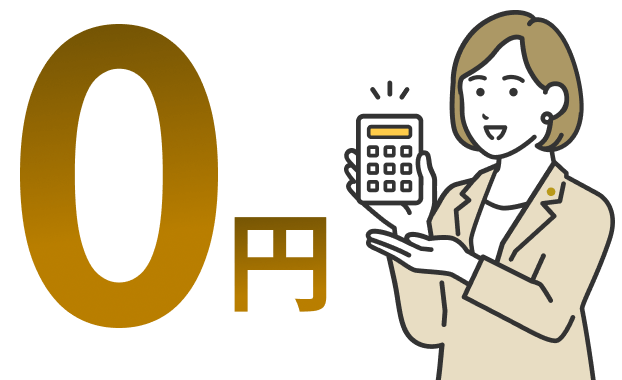独身の叔母の遺産相続はどうなる? 手続きの流れや注意点を解説
- 遺産を受け取る方
- 独身の叔母の遺産相続

最高裁判所の司法統計によると、山口県裁判所における令和5年の遺産分割事件の総数は172件でした。令和4年の総数が169件であったため、前年と比べると遺産分割にかかわる問題は、やや増加していることがわかります。
身近な方が亡くなった際は、亡くなった方の親や子ども、兄弟姉妹が相続にかかわることが多いでしょう。しかし、独身の叔母が亡くなった場合は、誰が相続するのか、手続きはどのように進めればいいのか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
亡くなった方に子どもや配偶者がいない場合、親や兄弟姉妹が相続することになるのが一般的です。しかし、親と兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が相続人となる可能性もあります。
今回の記事では、独身の叔母の遺産相続手続きについて、ベリーベスト法律事務所 山口オフィスの弁護士が解説します。
出典:「令和5年 司法統計年報(家事編)」「令和4年 司法統計年報(家事編)」(最高裁判所)


1、独身の叔母が亡くなったときは誰が相続する?
独身の叔母が亡くなったときは、誰が相続人となるのか、イメージしにくいかもしれません。こちらでは、誰が相続人となるのか、状況別に解説していきます。
-
(1)兄弟姉妹が相続人となる可能性が高い
独身の叔母が亡くなった場合、叔母の兄弟姉妹が相続人となる可能性が高いといえます。
そもそも民法では、亡くなった方(被相続人)の配偶者や子どもを法定相続人(亡くなった方の財産を相続できる方)と定めています。そのうち、配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の親族は、以下の上の順位から相続人となります。第1順位 子ども 第2順位 父母や祖父母 第3順位 兄弟姉妹
第1順位は子どもですが、独身の叔母の場合は子どもが存在しません。第2順位は父母や祖父母ですが、叔母が高齢である場合は、すでに亡くなっている可能性が高いでしょう。
この場合は、相続する権利が第3順位に移り、叔母の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は全員が相続人となり、遺産を分割して相続します。 -
(2)代襲相続で甥や姪が相続人となるケースもある
叔母の父母や祖父母が亡くなっているだけでなく、兄弟姉妹も、高齢ですでに亡くなっているケースもあるでしょう。その際は、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が「代襲相続」により相続人となります。代襲相続とは、本来であれば相続人となる方が相続開始前に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続することです。
代襲相続ができる方は、第1順位の子どもと、第3順位の兄弟姉妹に限られます。また、第1順位の代襲相続には制限がなく、子どもが亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫へと代襲します。
第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が代襲しますが、甥・姪の下の世代には代襲しません。そのため、代襲相続で甥・姪の子どもや、孫が相続人となることはありません。
2、独身の叔母が亡くなったときの相続手続き
独身の叔母が亡くなった際、まず行うべき相続手続きは、遺言書の調査と、その内容の確認です。遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容のとおりに相続手続きを進める必要があります。
以下では、遺言書の確認後に行う、一般的な相続手続きの流れを解説していきます。
-
(1)叔母の戸籍謄本を取得する
相続手続きをはじめる際は、叔母の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を確定させます。叔母が独身であったとしても、養子縁組をしている可能性などがあるため、必ず確認しましょう。
戸籍謄本は、叔母の本籍地を管轄している役所の窓口で請求できます。兄弟姉妹、または甥・姪が戸籍謄本を取得する場合は、叔母の出生から死亡までに移動した本籍地すべての役所に請求しなければなりません。特に本籍地の移動が多いと、手間がかかるうえに抜け漏れが発生するリスクがあります。
なお、弁護士に依頼すれば、「職務上請求」として依頼者の権利を行使するのに適法な範囲で戸籍謄本の調査が可能です。戸籍謄本の調査に不安がある方は、弁護士に相談しましょう。
ちなみに、2024年3月1日に、相続人が、相続人の確認に必要な戸籍を、最寄りの役所で一括して請求できる制度が始まりましたが、この制度は甥・姪は使えないのでご留意ください。 -
(2)叔母の財産を調査する
遺産分割を進めるためには、叔母の財産をすべて調査しなければなりません。叔母が亡くなった時点で保有していた財産すべてが、相続財産として遺産相続の対象となります。
具体的には、以下のようなものが相続財産に含まれます。- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券
- 自動車
- 貴金属・骨董(こっとう)品
- 著作権などの知的財産権
- 借金
- ローン
- 未払いの税金や医療費
相続財産の種類が多いと、調査に手間と時間がかかります。相続人だけでの調査が難しい場合は、弁護士への相談を検討してみてください。
-
(3)遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が明らかになったら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合う手続きです。
遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で各相続人の取り分を決めることが一般的です。
相続人全員が合意したら、合意した内容を記載した「遺産分割協議書」を作成しましょう。相続人間で意見が分かれて話がまとまらない場合は、弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。弁護士は、協議をスムーズに進めるためのアドバイスができるほか、依頼者の代理人としてトラブルを回避しながら協議を進めることが可能です。 -
(4)相続税の計算と納税をする
遺産分割協議と同時に、相続税の計算と納税を行うかどうかを検討します。
そもそも申告不要な場合があり、下記の課税遺産総額が-またはゼロの場合は申告不要です。課税遺産総額は以下の計算式で算出できます。課税遺産総額=相続財産の総額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)
なお、相続税の申告には期限があり、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
遺産分割協議が終わらなくても10か月以内に申告はしないといけないので、10か月以内に未分割のまま申告するか、分割を終えてから申告するかを検討しつつ、遺産分割を進めていかなければなりません。
お問い合わせください。
3、相続手続きの注意点
相続手続きを進める際には、いくつかの注意点があります。相続手続き中に見落としがちなポイントについて、具体的に見ていきましょう。
-
(1)相続放棄する選択肢も考慮する
叔母が亡くなり相続人となったときは、相続放棄する選択肢も考慮しましょう。相続放棄とは、相続人が亡くなった方の財産や権利義務を一切引き継がずに放棄する手続きのことをいいます。
相続放棄を検討すべきケースは、以下のとおりです。- 預貯金や不動産といった財産よりも借金やローンなどの負債が多い場合
- 遺産相続のトラブルに巻き込まれたくない場合
相続放棄する場合は、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。申述期限は、相続が開始したことを知ったときから3か月以内のため、なるべく早く相続財産を確認し、期限に間に合うように手続きをしましょう。
-
(2)遺言書の内容により甥姪が相続できない可能性がある
遺言書があった場合、その内容は原則として、民法で定められた法定相続人や相続順位などよりも優先されます。
ただし、第1順位や第2順位の相続人には、最低限の取り分として「遺留分」があり、遺言書などで遺留分が侵害された場合は、取り戻し請求ができます。一方、第3順位である兄弟姉妹や、代襲相続人である甥・姪には、遺留分が認められていません。
したがって、亡くなった叔母が遺言書を作成していた場合、内容によっては甥や姪が相続できない可能性があります。たとえば、「特定の人物や団体に全財産を渡す」といった内容の遺言が残されていた場合、甥や姪は財産を相続できません。 -
(3)相続税の申告期限・金額負担に注意する
叔母の財産を甥・姪が相続する際は、相続税の申告期限と金額負担に注意しましょう。
先述のとおり、相続税の申告・納付は、相続が開始したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため、相続手続きは早めに進めていく必要があります。
また、配偶者や一親等の血族(子ども・親)以外が相続する場合は、相続税に「2割加算」される点にも注意が必要です。兄弟姉妹や甥・姪が相続するときは、基本的に2割加算の対象となり、想定よりも税負担が重くなる可能性があります。
4、遺産相続で困ったら弁護士に相談を
遺産相続の手続きは法律にもとづいて進める必要があり、特に初めて行う場合は多くの疑問が生じるでしょう。困ったときには、べリーベストに相談することをおすすめします。
相続問題をべリーベストの弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
-
(1)法的根拠にもとづいた適切なアドバイスができる
弁護士は、法的根拠にもとづいた適切なアドバイスが提供できます。
遺産分割は、遺言書の解釈や相続人の範囲・遺産分割の方法など、相続人だけでは判断が難しいケースもあるでしょう。相続問題の対応経験が豊富な弁護士であれば、相続に関するあらゆる相談に対応が可能です。
早い段階で弁護士に相談し、不安要素を解消することによって、スムーズな相続手続きを実現できます。 -
(2)相続人や遺産の調査をサポートできる
弁護士は、相続手続きにおいて相続人や遺産の調査をサポートできます。
遺産分割方法を確定させるためには、正確な法定相続人の調査と財産調査が必要です。しかし、相続関係や相続財産の内容が複雑な場合は、調査が難航する可能性があります。
このようなときに弁護士が「職務上請求」により、代理で調査を行うことで、トラブルを未然に防げるでしょう。相続人や遺産の調査に不安がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。 -
(3)相続人同士の間に入ることで円満な解決を目指せる
弁護士が相続人の間に入って交渉を行うことで、円満な解決を目指せる可能性があります。
相続人が複数いる場合、意見の対立やトラブルが発生するケースもあるかもしれません。弁護士は、相続人との交渉の代理人となれるため、もめている相続人と直接交渉する負担を軽減できます。
相続人同士で意見が対立している場合は、問題が深刻化する前に弁護士への相談を検討してみてください。 -
(4)税務についてはべリーベスト税理士法人との連携が図れる
ベリーベストグループには税理士法人があるので、税務については税理士法人と協力しながら解決を図ることもできます。
5、まとめ
独身の叔母の遺産相続では、兄弟姉妹、または代襲相続により甥や姪が相続人となる可能性があります。相続手続きを進めるには、叔母の戸籍謄本を収集して相続人を確定し、財産の全体像を調査しなければなりません。
手続きに不安があったり、相続人間でトラブルが発生したりした場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることで、スムーズに相続手続きを進められるでしょう。
相続手続きや遺産分割で悩んだら、ぜひベリーベスト法律事務所 山口オフィスの弁護士へご相談ください。経験豊富な弁護士が、ご相談者さまの権利を守るためにサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています