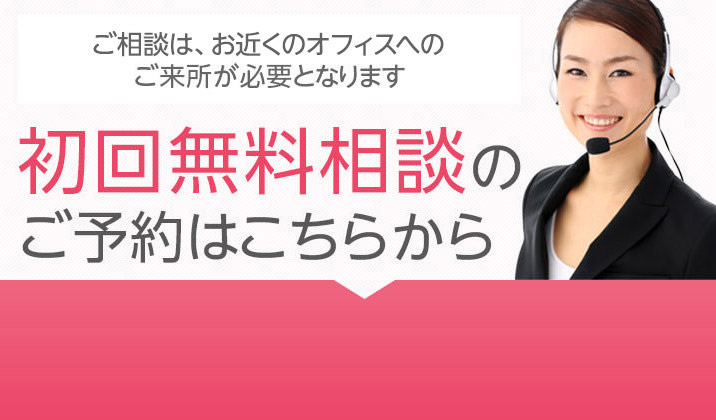養育費はいくらになる? 両親の収入による相場と決め方
- 養育費
- 養育費
- 収入

山口県の公表している保健統計年報によると、令和3年の山口県内の離婚件数は1875件でした。
離婚する夫婦のなかには、20歳未満の子どもがいることで、養育費について話し合う必要がある方もいるでしょう。養育費の金額を決める際は、相場を参考にすることをおすすめします。
当コラムでは、ベリーベスト法律事務所 山口オフィスの弁護士が、養育費の相場や算定方法について解説していきます。


1、養育費の相場は? 何が含まれているのか
離婚する際、子どもがいる方は養育費について検討する必要があります。養育費は、原則20歳未満の子どものための費用ですが、子どもが20歳をすぎても、経済的・社会的に自立をしていない場合は、引き続き養育費が必要となる可能性もあります。
こちらでは、養育費の相場や費用の内訳について紹介します。
-
(1)養育費の相場
厚生労働省が公表している「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、令和3年では、離婚した父親から受け取る養育費の平均月額は5万485円で、離婚した母親から受け取る養育費の平均月額は2万6992円でした。
つまり、母子世帯の養育費相場は5万485円、父子世帯の養育費相場は2万6992円ということになります。母子世帯は父子世帯と比べて、養育費をより多く受け取っている傾向にあります。 -
(2)養育費に含まれている費用
養育費に含まれる費用は、以下のとおりです。
- 生活費(食費、衣服代、住居費、水道光熱費など)
- 教育費(学費、教材費、塾代など)
- 医療費(薬代、通院治療費など)
- お小遣い
夫婦が合意すれば、これらの費用のほかにも、大学の入学費や習い事の月謝、修学旅行費用や海外留学費用などを養育費に含めることも可能です。詳しくは次章で紹介します。
2、養育費決定のベースとなる「養育費算定表」
養育費の金額は、話し合い次第で自由に決めることができますが、基本的には「養育費算定表」を参考に決定します。
養育費算定表とはどのようなものなのか、詳しくみていきましょう。
-
(1)養育費算定表とは
養育費算定表は、標準的な養育費の金額を簡単に計算できる早見表です。裁判所のウェブサイトで公開されており、養育費について裁判で決める際にも利用されています。
養育費算定表において、考慮されるのが子どもの人数や年齢、両親の収入です。子どもの人数が多い場合や、子どもの年齢が高いほど、養育費の金額は高くなっていきます。
また、養育費を支払う側(義務者)の収入が高く、養育費を受け取る側(権利者)の収入が低いほど養育費は高くなります。
なお、養育費の算定で考慮するのは、確定している前年度の年収です。権利者の年収には、児童扶養手当や児童手当、補助金や助成金を含める必要はありません。 -
(2)注意しておきたいこと
先述のとおり、養育費は基本的に子どもが20歳になるまで支払われます。養育費には、子どもが公立高校へ進学することを想定した教育費も含まれます。
したがって、私立の学校や大学への進学については、養育費は対応していません。義務者に対し、大学の教育費なども養育費として支払ってもらいたい場合は、夫婦での話し合いが必要です。
教育費をどこまで支払うかどうかは、家庭により事情が異なります。養育費の金額は、まず養育費算定表を参考にしながら、最終的には夫婦間で話し合って決定するようにしましょう。
お問い合わせください。
3、ケース別:養育費算定表による相場
先ほど解説したとおり、養育費の金額には子どもの人数や年齢、両親の収入が関係します。養育費算定表による養育費の相場を、3つのケース別にみていきましょう。
なお、子どもについては以下の条件で統一して養育費の金額を算定していきます。
- 子ども2人
- 2人とも0〜14歳
-
(1)義務者が会社員のケース
義務者が会社員(給与所得者)のケースでは、年収を正確に把握することが大切です。会社員の年収は、源泉徴収票の「支払金額」の欄を確認することで把握できます。
源泉徴収票の支払金額欄を確認した結果、会社員である義務者の年収が400万円、パート勤務である権利者の年収が120万円だったとしましょう。
このケースにおける子ども2人(いずれも0〜14歳)の、養育費算定表による養育費の相場は4〜6万円です。 -
(2)義務者が自営業者のケース
次は義務者が自営業者のケースをみていきます。会社員は、源泉徴収票を確認することで簡単に年収を把握できますが、自営業者は税法上の修正を考慮して年収を計算しなければなりません。
自営業者のケースでは、基本的に確定申告書に記載されている「課税される所得金額」に「社会保険料控除以外の所得控除の額」を加算することで年収を算出することができます。
加算対象になる「社会保険料控除以外の所得控除」は以下のとおりです。① 実際の支出を伴わないもの
- 雑損控除
- 寡婦、寡夫控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者(特別)控除
- 基礎控除
- 青色申告特別控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄付金控除
このように、確定申告書からも大まかな年収の計算は可能です。しかし、自営業者のなかには、事業との関連性が低い出費を経費として落としている方もいます。そのため、確定申告書とともに、帳簿や預金通帳も確認しておくことをおすすめします。
年収が把握できたら、養育費算定表を確認しましょう。
たとえば自営業者である義務者の年収が400万円、パート勤務である権利者の年収が120万円だったとしましょう。この場合、養育費算定表による養育費の相場は6〜8万円です。
ここからわかるように、義務者や権利者の年収が同条件でも、義務者が自営業者であれば、会社員の場合よりも養育費の金額が高くなる傾向にあります。 -
(3)権利者が専業主婦のケース
最後に、権利者が専業主婦のケースを紹介します。権利者が専業主婦の場合、収入は0円で計算します。
義務者が会社員で年収が400万円、権利者が専業主婦だったとしましょう。この場合、養育費算定表における養育費の相場は6〜8万円です。
また、義務者が自営業者で年収が400万円、権利者が専業主婦のケースでは、養育費算定表における養育費の相場は10〜12万円になります。
4、養育費の取り決めは弁護士へ相談を
養育費の取り決めでお悩みの方は、弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談するメリットにはどのようなものがあるのかみていきます。
-
(1)個別の事情に沿った養育費の金額を算定できる
養育費算定表は養育費の目安となりますが、個別の事情を加味すれば、定めるべき養育費の金額は変わるでしょう。
子どもに障害や病気がある場合や、子どもが20歳を超えても経済的・社会的に自立できないケースもあります。これらのケースでは、養育費算定表で算定した金額とおりに取り決めると、権利者と子どもの生活が困窮する可能性があります。
弁護士に相談すれば、養育費算定表を踏まえたうえで、個別の事情を考慮した養育費を算定可能です。 -
(2)相手との話し合いを代行できる
養育費の金額は、まずは夫婦で話し合って決めることになります。しかし、当事者同士の話し合いでは、感情的になってなかなか結論に至らないケースも少なくありません。
弁護士であれば、配偶者との話し合いを代行できるため、スムーズに養育費を取り決めできる可能性が高まります。養育費以外に、財産分与や面会交流、慰謝料などの離婚条件について話し合う必要があれば、併せて適切なアドバイスを行います。 -
(3)公正証書の作成をサポートできる
離婚後、取り決めた養育費を義務者に払い続けてもらうよう、誓約書を作成する方もいるでしょう。しかし、自作の誓約書では、万が一養育費などの支払いが滞っても、強制的に支払ってもらう力はありません。
一方、公証役場で作成する「公正証書」であれば、未払いトラブルなどを未然に防げる可能性が高まります。「支払い義務者は、義務の履行が滞った場合、直ちに強制執行を受けることに同意している」といった文言を公正証書に残すことで、養育費の支払いが滞った際、裁判を経ずに強制執行で義務者の財産を差し押さえることが可能になるでしょう。
公正証書は、夫婦で記載も可能ですが、弁護士に作成を依頼することをおすすめします。弁護士であれば、記載したい離婚条件に問題点がないかチェックすることができます。そのため、離婚後に離婚条件の認識不一致などによるトラブルが起こりにくいでしょう。
5、まとめ
養育費は、養育費算定表を参考にすることで算定しやすくなります。ただし、養育費算定表は個別の事情には対応していません。最終的には、夫婦で話し合い、家庭の状況に合った養育費を設定するようにしましょう。
また、弁護士に依頼することで、配偶者との話し合いを冷静に進めることができます。弁護士は養育費を含む離婚条件で、有利となるようサポートも可能です。
養育費の取り決めなど、離婚条件についてお悩みの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 山口オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています