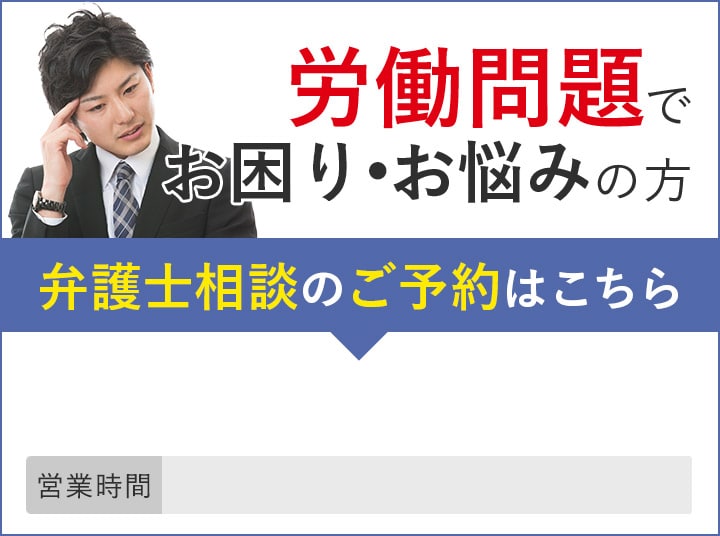労働者側からの労働審判とは? 手続きの流れや注意点を解説
- その他
- 労働審判
- 労働者側
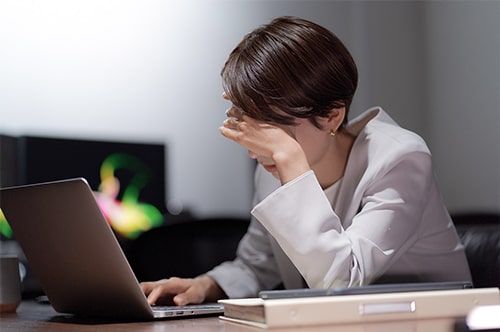
不当解雇や残業代の未払い問題など、労働者が会社との間の労働トラブルを解決するための手段として「労働審判制度」があります。労働審判制度は労働審判法に基づき設けられた制度です。
労働者側から労働審判を申し立てる場合には何点か注意しなければならないことがあります。労働審判手続の流れや注意点について、ベリーベスト法律事務所 山口オフィスの弁護士が解説します。


1、労働審判とは?
まずは労働審判の基本について解説していきます。
「労働審判制度」とは、労働者(従業員)と会社(事業主)間に発生した解雇や給料・残業代の未払いなどの労働トラブルを迅速・適正に解決するための制度です。
労働審判手続は、労働審判員(裁判官)1名と、労働審判員(雇用関係に詳しい知識・経験を持つ人)2名から構成される「労働審判委員会」が行います。労働審判委員会を介した調停・審判により、労働トラブルの解決を図るもので、非公開の手続きです。
労働審判の対象は労働者個人と会社間の労働トラブルであるため、「労働組合と会社のトラブル」や「労働者間のトラブル」は審理の対象になりません。
労働審判は原則として3回以内の期日で終わるため、迅速に解決するという特徴があります(次章で詳しく解説)。
2、労働者側が行う労働審判の期間や費用とは?
労働者が労働審判を行うと、どのくらいの期間や費用がかかるのでしょうか?
詳しくみていきましょう。
-
(1)労働審判の期間
労働審判は、原則3回以内の期日で終了します。したがって、申立てから2~3か月で終了するのが一般的です。
実際、裁判所の公表によると平成18年から令和5年までに終了した事件の平均審理期間は「81.7日」で、66.4%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。 -
(2)労働審判の費用
労働審判の申立てには、印紙代や切手代が必要です。印紙代や切手代は請求金額により異なりますが、相場は「1万から3万円程度」でしょう。
また、弁護士に依頼する場合には弁護士費用が別途かかります。
弁護士費用の内訳は以下のとおりです。- 相談料:法律相談のときに支払う費用
- 着手金:弁護士に依頼するときに支払う費用
- 日当:弁護士が裁判に出た場合に発生する費用
- 実費:郵送料や交通費などの費用
- 成功報酬:弁護士に依頼した案件の解決時に成功程度に応じて支払う費用
昨今では初回の法律相談を無料で行っている法律事務所も増えており、ケースによっても費用が増減するため一概にはいえませんが、労働審判の弁護士費用の相場は「60万から100万円程度」でしょう。
お問い合わせください。
3、労働者側が申し立てる労働審判の流れとは?
労働者側が申し立てる労働審判の流れを解説していきます。
-
(1)労働者が申立書を提出する
まずは、管轄の地方裁判所(本庁または一部の支部)に申立書を提出しましょう。
以下の支部が労働審判事件の取扱支部です。- 東京地裁立川支部
- 静岡地裁浜松支部
- 長野地裁松本支部
- 広島地裁福山支部
- 福岡地裁小倉支部
労働審判手続の管轄裁判所は、以下の3つのいずれかから選ぶことができます。
- 相手方の住所、居所、営業所、もしくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所
- 個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づき、労働者が現在就業している、もしくは最後に就業した事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所
- 当事者が合意で定める地方裁判所
また、申立書の他に以下の書類も必要です。
- 証拠書類(雇用契約書や就業規則、給与明細書など)
- 資格証明書(会社の登記事項証明書など)
- 収入印紙(申立書に貼付するのが通常)
- 切手
-
(2)期日指定・呼び出し
申立てが受理されると、裁判所に労働審判委員会が設置されます。特別な事由がなければ、第1回の労働審判期日の指定は、申立てがされた日から「40日以内」です。
この際、当事者双方に呼出状が送付されることになりますが、会社側には呼出状の他に申立書の写しが同封されます。 -
(3)会社側から答弁書等が提出される
会社側は、裁判所が定めた期日(目安は第1回の労働審判期日の1週間前)までに、答弁書等を提出しなければなりません。
-
(4)労働審判期日(原則3回)
解説してきたように、労働審判期日は原則3回で終了します。期日では、労働審判委員会が当事者から事実関係や主張を聞いて争点を整理し、必要な場合は当事者の関係者(労働者や会社の代表、従業員)から事情聴取を行いながら審理を行っていくのです。
第1回の労働審判期日の審理時間の目安は「2時間程度」で、ここで主張や証拠、反論が出そろいます。
第2回の労働審判期日は、第1回の労働審判期日の「2週間から1か月後」に設定されるケースが多いです。審理時間は「30分から1時間程度」で、労働審判委員会が当事者の間に入り調停(話し合いでトラブルを解決する手続き)のやりとりを行います。
多くのケースで、第2回の労働審判期日までには調停が成立し、労働審判手続が終了するため第3回の労働審判は開催されません。調停が成立しない場合は、第3回の労働審判が開かれます。 -
(5)調停または審判
労働審判委員会の仲介のもとで当事者同士が話し合いを行い、その結果、合意に達した場合には「調停」が成立します。成立した内容は裁判所によって調停調書に記載され、これにより調停手続きは終了です。条項の内容次第で、強制執行(債権者が債務者の財産を強制的に差し押さえる手続き)が可能になります。
話し合いがまとまらなかった場合、当事者の主張や証拠、審理の結果得られた当事者間の権利関係・手続きの経過などを踏まえた上で、労働審判委員会が「労働審判」を下します。労働審判はトラブルの実情に即した判断のことで、「2週間以内」に異議申立てをしなければ、労働審判が確定することになるのです。
異議申立てがあった場合は、労働審判は効力を失い訴訟手続きに移行することになります。
4、労働審判を申し立てる労働者側の注意点とは?
労働審判を労働者側が申し立てる場合、自分に不利にならないための注意点をみていきましょう。
-
(1)有利な事実を証拠に基づいて適切に主張する
労働審判では、労働者に有利な事実を示す証拠に基づいた適切な主張を行うことが重要です。
たとえば不当解雇について争う場合は解雇通知書や雇用契約書、人事評価書、解雇に関する会社間とのやりとりのメールや書面、録音などが有効になります。 -
(2)裁判所からの質問に適切に回答する
労働審判を取り仕切るのは裁判所が設置する労働審判委員会です。労働審判委員会からの質問に適切に回答できないと心証を悪くしてしまう可能性があるため、適切に回答する必要があります。
労働審判期日までに予想される質問への回答を整理し、当日適切に回答できるようにしっかりと事前準備をしておきましょう。 -
(3)労働事件に詳しい弁護士に相談する
労働者側に有利に労働審判を進めるためにも、労働事件の解決実績がある弁護士に相談するのがおすすめです。
労働審判手続は原則として3回以内の期日で審理が終了することになるため、充実した内容の申立書や、必要な証拠などの事前準備が重要になります。
弁護士に相談すれば、有利な証拠収集へのアドバイスや想定される質問への回答など、労働審判を自身に有利に進めていくためのアドバイスを得ることが可能です。
労働審判では会社側から提出される答弁書や証拠を検討して期日に適切な主張を行うことも重要になります。弁護士は、答弁書の検討も含め、申立ての準備から労働審判当日までサポートします。
また、弁護士が同席して、労働審判の場での主張や、裁判官からの質問への回答が不十分な場合に補足してもらうこともできるでしょう。
もちろん、労働審判手続は労働者個人だけで進めることも可能です。しかし、「短い期日で状況に応じた的確な主張や立証を行うためには弁護士に依頼した方がよい」と裁判所でも推奨されています。
不利な結果にならないためにも、早めに弁護士へ相談しましょう。
5、まとめ
労働審判は、労働者と事業主間の労働トラブルを解決する手続きです。原則3回以内の期日で終わるため、訴訟と比べて迅速に解決することができます。
労働審判を申し立てる場合、有利な事実を証拠に基づいて適切に主張する、裁判所からの質問に適切に回答する、労働事件に詳しい弁護士に相談するといったことが重要です。
特に、労働審判の「原則3回」という短い期日で、状況に応じた的確な主張や立証を行うためには弁護士に依頼することをおすすめします。
その際は、ぜひベリーベスト法律事務所 山口オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています